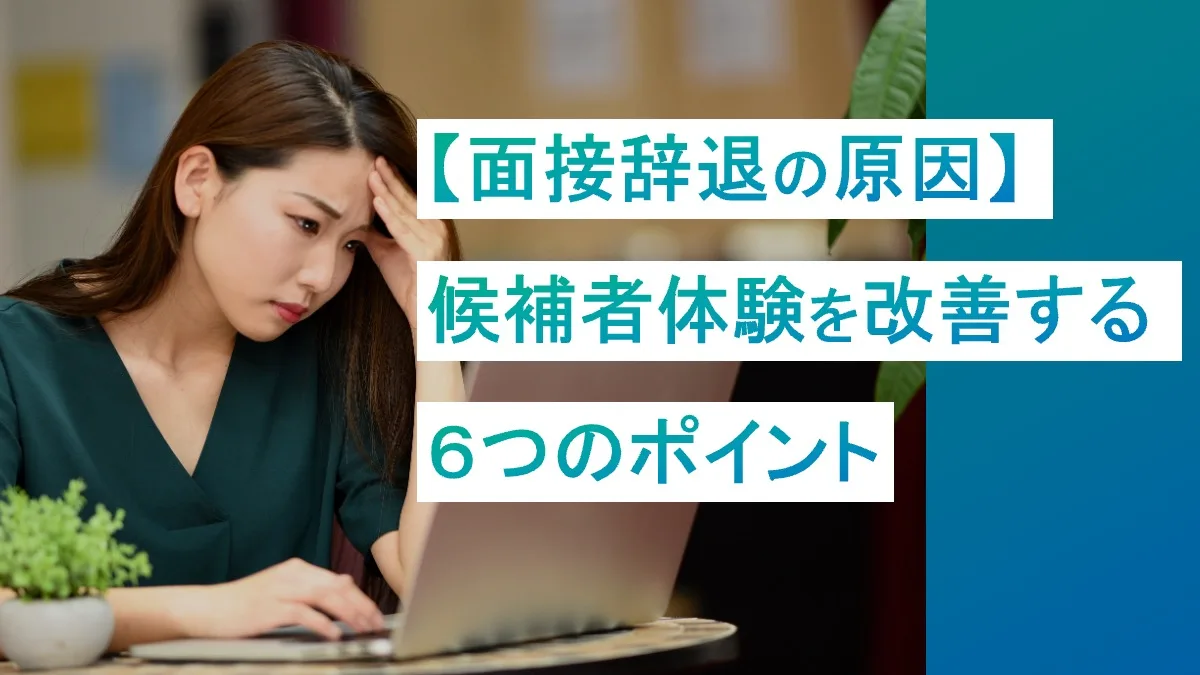採用の歩留まりとは?目指すべき平均値と改善方法を紹介
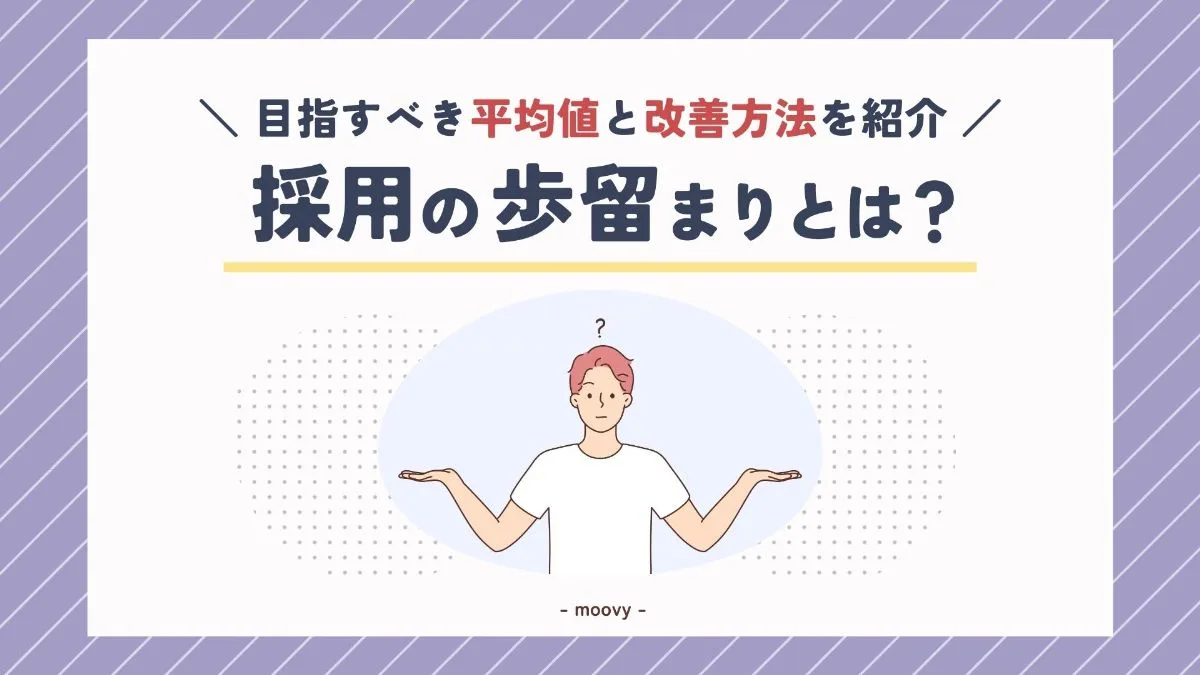
- 「内定を出しても辞退されてしまう」
- 「採用活動の成果が芳しくなく、ボトルネックもわからない」
- 「自社の採用活動の良し悪しが判断できない」
こうした悩みを抱えていませんか?
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う「新しい働き方」の登場、少子高齢化による採用活動の激化など、企業の人材獲得の難易度は年々上昇しています。
しかし、大手企業のように魅力的な雇用条件を提示できない企業が必ずしも不利な立場にあるわけではありません。
「採用の歩留まり」を算出し、ボトルネックを解消することで、採用成功に繋がる可能性があります。
当記事では、採用の歩留まりという考え方の重要性、算出方法、平均値の紹介に加え、採用の歩留まりを改善する具体的な手法を紹介します。
貴社の採用活動をより良いものにするためにも、当記事を参考にしてみてください。
売り手市場が続き、採用単価の上昇や手法の多様化が進む今こそ、設計が差を生みます。その設計を行う上で、欠かせないのが、「打ち手を知っておくこと」。
採用マーケティングを行うために、歩留まり(応募→内定→入社)を変える50の施策を体系化しました。ぜひこちらからダウンロードしてください。
採用の歩留まりとは

まず、採用の歩留まりについて、言葉の定義と重要性を紹介します。
採用の歩留まりとは
採用の歩留まりとは、応募から入社という採用活動のフェーズにおいて、あるフェーズから別のフェーズへの移行率を指す言葉です。
例えば、求人情報を見て応募した応募者が100人おり、そのうち50人が書類選考に合格する場合、書類選考の歩留まりは50%となります。
新卒一括採用のように、決められた期間や時期で多くの応募者を扱うときに用いられることが多い考え方ですが、人材会社を中心に中途採用の現場でも活用されます。
歩留まりが高いほど、効率の良い採用を行っていると言えるため、採用にかけるコストや時間が適切かどうかを判断する基準になります。
以下の弊社YouTubeチャンネルでも採用歩留まりについて詳しく解説しています。こちらも合わせてご覧ください。
採用の歩留まりの重要性
採用の歩留まりを見ることで、採用活動の効率を評価することができます。歩留まりが高いほど高効率な採用活動と言えるため、採用担当者は歩留まりを高めるために試行錯誤する必要があります。
また、採用活動の各フェーズの歩留まりを見たとき、著しく歩留まりが悪いフェーズがあれば、そのフェーズが採用活動のボトルネックになっていると考えられます。
採用担当者はボトルネックの解消に向けて、採用フェーズの問題点を洗い出し、改善を図る必要があります。
そのため採用の歩留まりは、採用活動の効率を高め、採用活動をより良いものにするために重要な考え方と言えます。
採用の歩留まりの算出方法と平均値

採用の歩留まりという考え方は、採用活動の改善において重要です。ここではその算出方法と、歩留まりの良し悪しを判断するための基準を紹介します。
なおここでの平均値はこちらを参考に掲載しています。
1.歩留まりの算出方法
採用の歩留まりは、特定の採用フェーズ(採用フェーズA)から別の採用フェーズ(採用フェーズB)に移行した人数の比率を表します。原則、以下の計算式で求められます。
=「採用フェーズBの人数(人)」÷「採用フェーズAの人数(人)」×100
実際の採用現場では、書類選考通過率や内定率のように、○○率と呼ばれることが多くあります。以下に代表的なものと、平均値を記載します。
2.【書類選考通過率】
■算出方法
「書類選考通過者数(人)」÷「応募者数(人)」×100
■平均値
30~50%
■活用方法の例
書類選考通過率が低い場合、求める人材像のハードルが高い可能性があります。この場合は、書類選考の基準を見直す必要があると考えられます。
また、雑多な応募者が集まっている場合も書類選考通過率は低くなります。この場合、求人情報を見直し、書類選考の基準に合致するよう内容を修正する必要があります。
3.【面接通過率】
■算出方法
「面接通過者数(人)」÷「面接実施者数(人)」×100
※場合によっては「面接通過者数(人)」÷「その前の面接通過者数(人)」×100で求めることもありますが、この場合、面接から次の面接を実施するまでに辞退をする応募者を考慮できません。
例えば、書類選考合格者に1次面接を行う企業で、書類選考合格者が100名いる場合を想定します。100名の内80名が1次面接を実施でき、そのうち30名が1次面接通過となった場合、分母に何を取るかで面接通過率は変わります。
分母を「1次面接実施者」にした場合、1次面接通過率は38%です。一方で分母を「書類選考合格者」にした場合、1次面接通過率は30%となります。
■平均値
1次面接通過率:30%
最終面接通過率:50%
■活用方法の例
面接通過率が低い場合、求める人材像のハードルが高い可能性があります。この場合は、書類選考の基準を見直す必要があると考えられます。
また、雑多な応募者が集まっている場合も書類選考通過率は低くなります。 この場合、求人情報を見直し、書類選考の基準に合致するよう内容を修正する必要があります。
4.【内定辞退率】
■算出方法
「内定辞退者数(人)」÷「内定者数(人)」×100
■平均値
7.9%
■活用方法の例
内定辞退率が高い場合、選考フローの中で応募者に対する魅力付けができていない可能性があります。応募者のスキルを判断するだけでなく、面接の中で応募者にどのような価値を提供できる会社なのかを伝える必要があります。
5.【内定率】
■算出方法
「内定者数(人)」÷「応募者数(人)」×100
■平均値
4.0~5.0%
■活用方法の例
「何人内定者が出たのか」という、採用において最も重要な指標です。採用計画を立てる際の最終的な目標値であり、採用活動に必要なコストを試算する基盤となる歩留まりです。
歩留まりを下げたいと考えている企業には採用動画がおすすめです。採用動画に関して気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
採用の歩留まりが低下する要因

採用の歩留まりを算出することで採用活動のボトルネックが特定しやすくなります。
ここでは歩留まりが低下する要因の代表例を以下の4つ紹介します。現状の採用活動を見直す際の参考にしてみてください。
- 1.求人情報が不適切である
- 2.応募者への連絡に不備や遅延がある
- 3.面接官の対応に不備がある
- 4.ネガティブな情報が拡散している
1.求人情報が不適切である
求人情報として公開している内容と、面接を通して実際に聞いた内容に乖離があると、選考フローの途中で応募者が辞退してしまうリスクがあります。
もちろん、ネガティブな情報を含めて赤裸々に記載する必要はありませんが、応募者に違和感を抱かせるほど実情と異なる内容を記載しないように気を付けましょう。
また、求人票や募集要項といったテキスト情報だけではなく、面接官にも情報を共有し、選考フローを通して応募者の心象を下げる要因を無くしていくことも重要です。
特に、条件面を重視する応募者の場合「仕事内容」だけでなく、「想定の残業時間」「転勤の有無」「休日出勤の有無」「有給消化率」「昇給・賞与の実情」といった項目にも注目します。
ベンチャー企業の場合、これら項目の全てを整えることは困難であることがほとんどかと思います。このような場合は、面接官に対して、これらの項目を応募者にどのようにつたえるかをすり合わせる必要があります。
2.応募者への連絡に不備や遅延がある
選考のスピードは採用の歩留まりに影響を与えます。
採用競合に先んじて優秀な人材を確保するために、企業はできるだけスピーディに選考を進めようとします。
そのため、内定までに時間がかかる企業は相対的に不利といえます。結果として、採用の歩留まり低下につながってしまいます。
株式会社マイナビ「中途採用状況調査2023年版」によれば、選考フローのスピードの平均値は以下のように報告されています。
WEB面接:19.4日、対面面接:19.8日
【応募から1次面接までの平均日数】
WEB面接:10.4日、対面面接:11.1日
【1次面接から内定までの平均日数】
WEB面接:9.0日、対面面接:8.7日
【内定から内定承諾受領までの平均日数】
WEB面接:7.2日、対面面接:6.9日
また、株式会社リクルートキャリアが採用担当者向けに行なったアンケート調査によれば、書類選考期間(応募から書類選考結果の連絡までにかかる期間)は、「1日以内」と答えた企業は24.7% 、「3日以内」が39.3% 、「1週間以内」は27.7% 、「2週間以内」が6.0% 、「1ヶ月以内」は2.3% という結果が得られています。
全体の約9割が1週間以内に書類選考を行なっているため、選考スピードがいかに重要な指標であるかがうかがえます。出典:転職の書類選考の期間はどのくらい?連絡がこない理由と対処法は?ー株式会社リクルートキャリア
応募者は早く就職や転職したいと考えているため、面接の日程調整が遅れたり選考期間が長いと、先に内定を出した他社に流れてしまいます。
選考フローを開示する、選考後はすぐに結果連絡を行う、選考回数をできるだけ減らすなど、内定までのスピードを早めることを意識しましょう。
3.面接官の対応に不備がある
「面接官の対応」も採用の歩留まりに影響を与える要素のひとつです。求人情報で「風通しがよく、誰でも意見を交わせる環境」と記載していても、面接官が高圧的な態度を取っていては説得力に欠けます。
また、応募者を正確に評価しようとするあまり、尋問のような面接を行っていては、応募者に自社の魅力的な情報を伝えて志望度を上げることができません。
採用活動は応募者が自社に合うかを見極めるだけでなく、応募者の目的を実現できる会社であることを説明して応募者の志望度を高める役割を担います。
企業が応募者を評価すると同時に応募者も企業を評価していることを忘れないようにしましょう。
4.ネガティブな情報が拡散している
SNSやクチコミサイトの投稿が、応募者の辞退につながることもあります。
エン・ジャパン株式会社「面接辞退のアンケート」によると、31%の応募者が辞退を決めた理由として「ネット上で良くない評判やウワサを知ったため」と回答しています。
出典:7,200人が回答!「面接辞退」実態調査 ー『エン転職』ユーザーアンケート
また、情報の拡散状況によっては、応募者本人が気にしていなくても家族から反対されることもあります。
採用の歩留まりを改善する方法

ここでは、採用の歩留まりを改善する具体的な方法4つを紹介します。
- 1.求人情報を見直す
- 2.スピーディな連絡ができる体制をつくる
- 3.面接官を指導・教育する
- 4.採用ブランディングや採用広報に取り組む
1.求人情報を見直す
採用の歩留まりが低下する要因のほとんどは、企業が求める人材像と実際の応募者との乖離によるものです。
企業が求める人材像を適切に求人情報に落とし込むことが、最も基本的な歩留まり改善方法といえます。
求人媒体や人材紹介会社に提供する募集要項、コーポレートサイトや採用ホームページなどを見直しましょう。
具体的には、以下のような点を見直すことができれば良いでしょう。
- ・募集する職種に合った適切な媒体を使用しているか
- ・具体的に仕事がイメージできるような職種名になっているか
- ・1日の業務の流れを記載しているか
- ・採用コンセプトが明確になっているか
このとき、求める人材像の解像度の高さが、求人情報の出来を左右します。
これには「採用ペルソナ」の設定が役立ちます。以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。
合わせて読みたい:採用ペルソナの作り方を徹底解説!求める人物像を獲得する有効な手法とは?
2.スピーディな連絡ができる体制をつくる
選考のスピードは採用の歩留まりに影響を与えます。選考フローを開示する、選考後はすぐに結果連絡を行う、選考回数をできるだけ減らすなど、内定までのスピードを早めることを意識しましょう。
少数精鋭で採用活動を行っていたり、採用と他の業務を兼務しているなど、採用に対して多くの時間を割くことが難しい場合は、採用活動を仕組化する必要があります。
採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)の導入、応募者向け連絡をテンプレート化するなど、社内の情報流通が滞りなく進むよう工夫しましょう。
具体的には、以下のことをルールとして取り入れることができれば理想的です。
- ・応募があった際は24時間以内に連絡する。
- ・面接の1~2日前には、リマインドの通知を行う。
- ・合否の連絡は、最長でも3日以内に行う。
- ・LINEなど幅広い年代で使用されているコミュニケーションツールに変更する。
以下の記事では採用通知メールの書き方を詳しく解説しています。段階ごとのテンプレートもありますので、ぜひご活用ください。
合わせて読みたい:コピペ可!採用関連メールの書き方と雛形8選【シチュエーション別にまとめました】
3.面接官を指導・教育する
安定成長期に入ると、次第に経営陣が採用に関与する機会は減ってきます。取り得る採用手段も幅広くなり、人材紹介、採用特設サイトなども視野に入ります。
部署ごとにカラーが出始め、現場で必要な人材を部署の裁量で採用することも増えてくるでしょう。
経営陣の立場として意識すべきなのは、現場に寄り添い過ぎないことです。部門長に部署を任せているとはいえ、現場業務の延長線上に会社の目指す姿があるとは限りません。
一見すれば積極的に採用をしているように見えて、実際は既存の業務を維持するために、とにかく人員を集めているだけ、ということもあり得ます。
部門の現状を加味しつつも、部門の課題は「本当に採用でないと解決できないのか」に立ち返り、安直な採用になっていないかチェックすることを怠ってはいけません。
具体的に以下のような教育、指導を行ってみるのも良いでしょう。
- ・面接官は安心感を与える存在であることを伝える
- ・昔と違って、今は「売り手市場」で企業が「選ばれる」環境にあることを理解してもらう
- ・質問すべき内容と、してはいけない内容を意図と具体例を教える
- ・どこに着目して評価すべきかを明確にする
- ・社内でロールプレイングを行い、求められる面接官の役割ができているか1回は必ずチェックする
- ・求める人物像の解像度を上げて、共有する
4.採用ブランディングや採用広報に取り組む
企業のブランドイメージを高めることで、応募者に魅力的な企業として認知してもらいやすくなります。
「採用ブランディング」は、長期的な視点で企業のブランド認知度を高め、優秀な人材を獲得することを目的とした採用手法のひとつです。
自社ならではの魅力を発信し、企業認知度や応募者の入社意欲を高めるなど、「働く場所」としての企業を戦略的にブランド化していくことで、採用の歩留まりが改善されていきます。
また、「採用広報」は、企業の採用活動を広くアピールすることを目的とした採用手法のひとつです。例えば、
- ・求人情報を掲載する媒体の選定
- ・求人情報の配信方法の改善
- ・求人情報をアピールするクリエイティブの制作
- ・SNSを活用した情報発信
求人情報を掲載する媒体の選定や求人情報の配信方法の改善、求人情報をアピールするクリエイティブの制作、SNSを活用した情報発信など、様々な手段で企業のポジティブな情報を発信します。
インターネットやスマートフォンの普及により、応募者の情報収集手段は各段に増加しているからこそ、様々な媒体で企業の情報を発信することで、応募者やその家族の印象を改善することができます。
採用ブランディングの詳しいやり方はこちらの記事で解説しています。気になる方はご覧ください。
採用にお困りの方へ

採用の歩留まりは、企業の採用力向上に直結する重要なデータです。採用の歩留まりを算出し、ボトルネックとなっている要因を見極め、改善を図ることで、より良い人材の採用を実現することができます。
自社で活躍しうる人材を獲得し、企業の成長を早期に実現するためにも、当記事を参考にしていただけると幸いです。
ただし、本当に重要なのは、経営陣が企業のビジョンをしっかりと描き、その実現に必要な人物像を解像度高くイメージし、その人物像に刺さる表現で自社の魅力を伝えられるかどうかということです。
これはベンチャー企業に限らず、全ての企業に共通して言えることでもあります。テクニックを過信せず、必要なことを着実に行うことが、結果的に採用成功の近道であることを忘れないでください。
採用動画のmoovyは、創業ストーリーや経営理念、社員のインタビューなどを制作・配信する採用動画メディアです。動画は1本あたり30秒。要点を絞った情報発信になるため、視聴に対する求職者の心理的ハードルを下げることができます。
また、「企業理念や企業の価値観」や「現場で活躍する社員の生の声」など、 テキストだと分かりにくい社員の人柄やカルチャーを紹介できるため、応募者の深い企業理解をサポートすることが可能です。
応募者がSNSやYoutubeなどの動画メディアに触れる機会は今後も増加していきます。限られた時間で企業のポジティブな情報を発信する手段として、動画は効率的な採用広報の手段といえます。ぜひmoovyの動画サービスの活用をご検討ください。